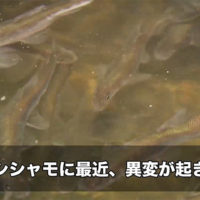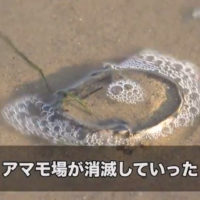近年、有明海から、天然のアゲマキがいなくなっている。
ハマグリなどと同じ種類の二枚貝アゲマキは、もともと有明海では、煮つけや味噌汁など、様々な料理に使われていた特産品。しかし、その漁獲量は、平成になってドンドン減り続け、1994年以降はゼロに。その原因は、佐賀大学 低平地沿岸海域研究センター特任助教授の藤井直紀さんによると、「原因のひとつは、貧酸素。酸素が減っていく現象で、海中の酸素が少なくなると、生き物が減っていくことになります。それから、泥の状態が悪いということも、ひとつの原因かもしれません。例えば、有毒ガスである硫化水素が発生することで、生き物が生きづらくなります」と話す。海中の酸素が様々な原因によって減少。また、海底に状態が悪い泥があり、そこから有毒ガスが発生するなど、多くの要因が絡み合ってアゲマキは減ってしまったという。
そこで、佐賀県では、アゲマキの復活に約20年前から取り組んでいる。佐賀県有明水産振興センターは、アゲマキの赤ちゃんである稚貝100万個の生産に成功。その稚貝を、産卵と成長に適した場所を探し、何度も場所を変えながら、2009年から毎年、冬に100万個 放流している。その結果、その後も試験養殖を重ねたことで、天然の漁場でアゲマキの稚貝が育っていることが確認できた。稚貝は佐賀県鹿島市周辺の海で多く増えているため、今後、有明海全体に広げ、将来的に、持続的に水揚げが出来る状態まで取り組みを続けたいとしている。
かつてのように、有明海で育ったアゲマキを食べられる日が着実に近づいている。
素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin佐賀」
協力:株式会社サガテレビ