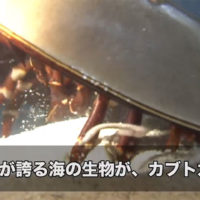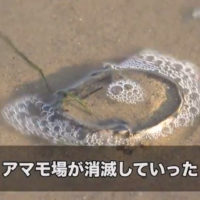水族館は日本全国に100カ所以上もあり、国土面積あたりの数にすると世界一とも言われています。各地の水族館では展示以外にも重要なお仕事が…。それが飼育・研究です。福井県の越前松島水族館で飼育・研究されているのが、ダンゴウオ科の「コンペイトウ」。こぶ状の突起が菓子の金平糖に似ていることが名前の由来です。この水族館では約30年前から飼育を始め、2008年には日本で初めて繁殖に成功しました。すると、驚きの事実が…。「ある日突然、水槽の中にコンペイトウの赤ちゃんが大量に現れた。そのとき初めて小さい方がオスだと判明し、これまで15年間 展示していたのは全てメスだったとわかった」と飼育員の笹井清二さんは言います。これまで別の種類の魚だと考えられてきたのが、コンペイトウのオスだとわかったのです。この魚はオスとメスで体の大きさが違い、メスの方が大きくなるとのこと。現在、館内には「コンペイトウハウス」が設けられ、稚魚から成魚まで100匹ほどを飼育。水族館のアイドルとして人気となっています。
一方、滋賀県には国内初の快挙を成し遂げたスポットがあります。それが滋賀県立琵琶湖博物館です。ここでは、2010年度からツチフキの繁殖に取り組んでいます。ツチフキとはコイ科の淡水魚で、水底のエサを土ごと吸い込んで吐き出すことから名づけられたそうです。しかし、環境悪化によって個体数を減らしているそうで、淀川ではすでに絶滅したと言われています。そんな中、この博物館では、これまで10世代・950匹以上(※取材当時)の繁殖に成功。その繁殖技術が評価され、全国で初めて日本動物園水族館協会の初繁殖認定を受けました。学芸員の川瀬成吾さんは「保護活動がもっと盛んになって絶滅危惧種が減って欲しい。ほかにも、日本の淡水魚でまだ繁殖技術の確立していない種類がたくさんいるので、ツチフキの成功を次のモチベーションにしていきたい」と抱負を述べています。
さらに、沖縄美ら海水族館でも、希少な海洋生物が飼育・研究されています。それが、世界的に絶滅危惧種とされているウミガメです。水槽の隣には、仔ガメを展示する「ウミガメ育成プール」があり、アオウミガメ、アカウミガメ、タイマイという3種類の繫殖・育成を行っています。このカメ達にはそれぞれ全く違う特徴があるそうで、一般財団法人 沖縄美ら島財団・事業部・海獣課・ウミガメ係の小淵貴洋さんは「食べている物が違うので顔の形も変わる。タイマイは岩などに被覆している海綿動物等を剥がして食べるのでクチバシが細長くなる。アオウミガメは海そうを食べるので、クチバシにギザギザがついている」と言います。さらに、仔ガメ特有の行動もあるそうで「生まれてすぐに外洋で生活する仔ガメは、流藻や流木等とともに漂流します」と小淵さんは説明。水族館ではこういったウミガメの生態を知ってもらう展示や、成長したウミガメたちを放流する活動まで行っています。今後について小淵さんは「どんどん公表できるものを増やしていって、ウミガメが絶滅危惧種と言われないような環境になって欲しい」と語っています。
素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトinふくい」 「海と日本プロジェクトin滋賀県」 「海と日本プロジェクトin沖縄県」
協力:福井テレビジョン放送株式会社 びわ湖放送株式会社 琉球放送株式会社