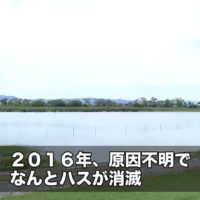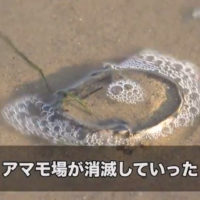フレンチで使われる高級食材シタビラメ。
岡山県を代表する魚種で、「げた」と呼ばれ親しまれている。しかし、近年、そんなげたやカレイなど、海底に住む魚の漁獲量が激減。1998年は900トン以上も獲れていたが、最近では270トンほどと3分の1以下になってしまった。
その原因の1つが、海の底に溜まったヘドロ。
このヘドロから発生する有害なガスの影響で、海底の環境が悪化しているのだ。
そこで、岡山県では、この状況を改善するため、2012年から大多府島の沖合で、ある取り組みを開始。それが、カキ殻を使ったヘドロの浄化。海の底に、なんと小学校のプール1杯分、およそ550㎥ものカキ殻をまいている。水圏環境室専門研究員の古村振一さんによると、「カキ殻を敷くとヘドロを分解しやすくなる。環境が悪くなると、黒っぽい泥になって、灰色の泥だと環境は問題ない」と話す。カキ殻には無数の細かい穴が空いていて、空気がたまりやすい。そして、ヘドロは、酸素を与えることで、バクテリアの活動を促進させ、分解することが出来る。そのため、カキ殻を敷くと、通常よりも酸素に触れやすい状態となり、ヘドロが分解されやすくなるという。
実際に、カキ殻の効果は出始めていて、ゴカイなど魚のエサとなる生き物が増加。魚が住みやすい環境に変化しているという。調査したダイバーによると、「(ほとんどいなかったカサゴですが、)今日はカサゴを10数個体、確認することができました。カキ殻の効果というのがでていると思います」と話す。ちなみに、この取り組み、カキ殻の処理にも役立っている。カキ生産量が全国3位の岡山県では、年間およそ1.5万トンものカキ殻が発生。これまでは、家畜の飼料や運動会の白線用の炭酸カルシウムとして利用されていたが、カキ殻を環境改善の資材として利用することで、またひとつ新たな活用策が確認され、岡山県にとっては一石二鳥の取り組みなのだ。しかし、漁獲量の回復には、まだ長い年月がかかるという。また、ヘドロ自体が無くなるわけでもない。
古村さんは、「これだけでヘドロが減るわけではない。皆さんが海を汚さないようにする取り組みをしてくれることが大切だと考えています」と語った。
素材提供:日本財団「海と日本プロジェクトin岡山」
協力:山陽放送株式会社